|
第4回ボイルドエッグズ新人賞受賞作
|
鴨川ホルモー 万城目 学
(エントリーNo.13/Aフィクション部門)
|
| 作品内容: ホルモー? ホルモンでなく、ホルモー? かつての王城の地、ここ京都で脈々と受け継がれてきた「ホルモー」とはなんぞや!? 主人公安倍は大学に入学してまもなく、京大青竜会と名乗る謎のサークルから勧誘を受ける。その新歓コンパで、安倍は同じ新入生の女子に一目ぼれしてしまう。一方で徐々に明らかになるサークルの隠された目的とは……。壮大なる歴史的スケールで、冴えない大学生の悲喜こもごもの日常を描く奇想青春ファンタジー! |
| 著者紹介:万城目 学(まきめ・まなぶ)1976年生まれ、29歳。大阪府出身。京都大学法学部卒。化学繊維会社に勤務ののち、現在無職。東京都在住。 |
■選考過程
1 第4回ボイルドエッグズ新人賞には、総数23作品のエントリーがありました。
2 各選考委員は、作品すべてに目を通し、それぞれ評価リストを作成しました。
3 その評価リストをもとに、10月下旬、選考会を催しました。
4 選考会では、新人賞の最終候補作として、墨野貴子『マイラ』、昭島瑛子『僕の半分』、万城目学『鴨川ホルモー』、俊多『とりかえっこ』、南野海『大和撫子王女様』、沖田リエ『若草』の6作品を選び、検討しました。
5 最終的に、万城目学『鴨川ホルモー』が満場一致で受賞作と決まりました。受賞作は近く産業編集センター出版部より単行本として出版されます。刊行の詳細はあらためて告知します。
|
|
■選考委員講評(到着順)
|
|
●千木良悠子
今回はとっても充実したラインナップで、読んでいて楽しいものが多かったです。
まず「僕の半分」ですが、等身大の語り口で、スキッと爽やかレモン味でした。自分をモテると思ってる主人公のぺらっぺらな性格設定も、アリガチの展開に偶然の連続という物語の筋立ても逆に若者らしくって心地よく、ただ惜しむらくは、ラスト、なぜかどこまでも偶然に、主人公たちが実のお父さん・お母さんと町の鄙びた洋食屋さんやら代官山のブティックやらで巡り会って、それで「自分探し」完了、とオチをつけてしまっている。オチてません。これは、オチてませんよ! 自分探しをしていたつもりがいつのまにか親探しになっている。これでは困ります。
それから「若草」。これも耽美の風味も爽やかな、すてきな作品だなあと思いました。まず主人公の女だか男だかわからない人と、その恋人の人間だか竜だかわからない人とのカップルが良い! そして若草姫が実の兄を慕う心が、アツい。でも人物の名前が呼び名と本名と二つあったり、重要人物なのに「中将」「中納言」としか書かれていなかったり、ふとするといつのまにやら誰が誰だか、何が何やら、わからなくなってしまうのです。読者にはバカも天才もいるでしょうから、覚えられない人もいるかと思います。平安ファンタジーらしい複雑な名前をつけるのに困難を覚えたら、「マヨネーズの中将」とか「ポン酢中納言」とか「牡蠣バターの内親王」とかでも最悪、良いわけですし(ダメですかね!)、小説なのですから、もう少し自由に、踊るように、お花畑を飛び回るモンシロチョウのように、軽々しく想像力の翼をはためかせて勝手な名前をつけてしまっても構わないのではないでしょうか。この作品の書き手は、ある部分ではイマジネーション豊かなのに、別の部分では、どこか、ソースとなるような既存のファンタジー小説、ありものの作品の記憶に引き摺られて不自由なさってる印象がありました。しかし、若草の怨念が晴れていく過程など、大いなるドラマとサスペンスがあり、たいへん読み応えがありました。
そして「マイラ」。一読したときはあまりのポエジーに目眩がして、これは素晴らしい、天才的な感性を持っていらっしゃると戦慄したのですが、だんだん世界観の過剰さに警戒心が芽生えてしまいました。「マイラ」である男のひとり語りと、小学生の一人称部分は悪くない。自意識過剰ぎみな文体が、世間から疎外されたキャラクターを描くためにうまく機能しています。が、とにかく教授の伴辰比古の人物像が曖昧すぎます。彼はとにかく喋り過ぎだし、とても40代の男性には見えない。物語の半分か、それ以上の担い手であるはずなのに、どうも共感しづらいキャラクターに育ってしまっている理由は、いわゆる登場人物と作者の間の距離感、という問題だと思います。小説の登場人物は他人です。親兄弟や友人、町ですれ違ったおっさんや、TVの中の芸能人たちと同じように。行ったこともない砂漠の国でこの瞬間に飢えて亡くなっている知らない方々が他人であるのと同じように、自分の頭で考えた自分の大切なキャラクターたちは、全員他人です。よくわからんやつらです。例えば20代後半である私なんかには、40代の大学教授が考えていることなんて、完全には理解できないと思います。ですが、もしキャラとして40代の教授を登場させたいなら、20代でも0歳でもダメ、というのなら、身近な40代、知り合いでも芸能人でも、40代っぽいお菓子とか歌とか色とか形でいいから、思い浮かべてみようと思います。そして、共感できそうなところを探してみるのです。一点の光のような共感のツボ、そいつを頼みの綱に40代を想像していると、考えていたキャラクターが全然別の方向に進み始めたり、自分の考え方とは180度違う思想を語りだしたり、意外なことがより、起こりやすくなるような気がしませんか。有り体に言えば、距離を取るということです。単純に、普段自分で考えていることをそのままキャラに喋らせるよりも、さらに面白い創作体験ができるのではないでしょうか。あんたなんか知らない。他人、他人。罵りながら、唾を吐きかけながら、キャラたちをよく愛したげてください。
ついでに付け加えると、この作品ではSMが取り扱われていますが、マキャベリの「君主論」やヒトラーのファシズム、といった思想っぽい用語を安易にSMに結びつけると、本物の教授やら町の物知り爺さんやら、本当に哲学を愛しているうるさ方と、それから本当にSMを愛している方々が、一斉に眉をぴくっと上げます。怖いです。思想や歴史にまつわる用語は、もっとビビりながら、あるいはもっと威丈高に、相手の様子を伺いながら、使ってほしいと思います。大胆に、時に貞淑に。もっとしなやかに、もっとしたたかに。私はペダンティックな作家ってとても好きなのですけれど、どんどん勉強なさって、詐欺師のような饒舌さを身につけて、湯水のように贅沢に才能を浪費して、もっとタフになって、もっとラフになって、読者をアッと言わせてほしいと期待しました。
そして最後に、今回の受賞作について。こいつは面白い!
「鴨川ホルモー」は京都に伝わる奇怪な競技(じつは完全なるでっち上げ)の物語です。私には主人公の安倍と凡ちゃん頭の楠木ふみが、南海キャンディーズの山ちゃんとしずちゃんに思えてしかたありません。ふたりを主役に、ポール・バーホーベン監督でハリウッド映画を撮ってもらいたい……! もちろん、式神たちはいい案配のCGで。レーズンがすぽんと「オニ」たちの頭の中に入るところなど、ぜひ映像化するべきです。DO
YOU KNOW "ONMYODO"?(陰陽道)」東洋の神秘、日本のミステリー、碁盤の目の中のファンタジーですよ。出だしが多少勿体ぶりすぎているのと、あとラストがどうしても不満、という口惜しさは残りますが(恋愛がうまくいったことと物語の決着とはまったく関係ない。主人公の安倍、最後くらいちょっと成長すべき。私の考えたオススメのラストなんですが→「レナウンルック」よりさらに下らない、目を覆うような代替わりの儀式が行われて、狂乱状態のうちにいつの間にか終わる。敵も味方もどーでもよくなって、意味のわからぬ一体感が生まれ、安倍たちの代の部は過去最強の破壊力を持った団体になるのか……?と予感だけ残しつつ、テキトーにEND。どう? 1000円で買ってくれないかしら)あとは、片思いの経緯も、試合も儀式のシーンも、とても面白かった。笑いをこらえて読んでいた。
京大と言えば、「太陽の塔」って本が少し前に流行ってたようで、かぶってると言われないか気になりますが、私はこの作品のほうが好きです。集団でひとつのことに熱中することの喜び、興奮が健康的に描かれている。健康というのは、特に最近の小説に欠けている重要なキーワードなのではないでしょうか。
良い作品に出会えて、嬉しく思います。選考の機会をいただいたことに感謝いたします。
|
|
●三浦しをん
今回は非常にレベルが高く、最終選考に残った作品を、どれもおもしろく拝読しました。そのなかで『鴨川ホルモー』が、満場一致で受賞作となりました。
私が今回、応募作を拝読しながら考えていたのは、「小説のリアリティーとはなんなのか」ということです。言い換えれば、「小説内での『偶然』はどこまで許されるのか」ということでもあると思います。それを念頭に置きながら、私が特に気になった(気に入った)『鴨川ホルモー』『マイラ』『若草』の三作品を中心に講評させていただきます。
『鴨川ホルモー』は、あらすじを紹介することが困難です。あまりにもアホらしく突拍子もないことに、登場人物たちが真剣に取り組んでいるからです。しかしそのアホらしさが、学生たちのモラトリアムぶりにふさわしく、こなれた文章、ユーモアの感覚、適度な客観性を保った主人公など、とても楽しく魅力的な小説でした。読んでいるうちに、登場人物たちが取り組む「アホらしいこと」も、実は映像化にはうってつけの題材なのではないかと思われてきたほどです。
しかし、これはあくまで小説なので、注意すべき点もあります。「アホらしいこと」というのは具体的には、「ほかの人々には見えない小さな異形のものたち(千人規模)を戦わせあう」ことなのですが、陣形や戦術が情景としてうまく浮かんできません。「その陣形では負けてしまうのでは?」というような、説得力に欠ける部分が少々ありました。戦いのシーンの動きや時間経過などを整理し、もうちょっと緻密に具体性をもって描写したほうがいいと私は思いました。
これはたぶん、文章のメリハリの問題とも関係していると思います。とても読みやすく、リズム感のいい文章なのですが、やや饒舌すぎるというか、「流れる」部分があります。語りをグッと抑え、「タメ」の部分を作ることによって、盛り上がる部分(戦いや、人間関係の危機が訪れるシーン)での緊迫感がよりいっそう増すでしょう。緻密な描写が必要なシーンと、読者の想像に委ねるべきシーンとの、文章の密度について一考してください。
主人公の安倍くんが、最後まで受け身すぎるのも気になります。饒舌に内省し、積極性を見せることに恥じらいを覚える安倍くんの性格ゆえだとは思います。しかし読者は、安倍くんに身を委ねて物語を楽しんでいるわけですから、ある程度は安倍くんの積極性と成長ぶりを実感できないと、読後にすっきりしません。現実では、人間はそうそう成長しませんし、積極的になりきれないものですから、あまりやりすぎると鼻白む。小説内でのキャラの成長はどのへんまで許され、読者は不自然さや反発を感じることなくカタルシスを得られるのか。非常に塩梅が難しいところではありますが、バランスを探ってみてください。
『マイラ』と『若草』はそれぞれ、作者に書きたい世界があることが強く伝わってくる作品でした。よりよく伝えるために、気をつけるといいのではないかと思った点をあげます。
まず、『マイラ』について。出だしから比喩を頻発させるのは避けたほうがいいでしょう。私も比喩を考えるのも使うのも大好きなのですが、ひとによっては「気取っている」「読みにくい」と受け取る場合があります。もちろん、登場人物の特性を表すための重要な描写だということはわかりますが、読者を物語内に引き込むためには、最初から比喩を連続して使うことは、避けたほうが無難です(これはきわめて表層的な、小説を書く際のテクニックですので、あくまでケース・バイ・ケースです。納得いかなければ聞き流していい程度の問題です)。
また、ホームレス支援者の公演や、シンちゃんのSM人生観、女王さまの最後の独白など、ちょっとしゃべりすぎるというか、作者の「生」の声が出すぎているように感じられる部分がありました。一人称の場合は特に難しいのですが、主義主張はできるだけ、登場人物の行動や習慣など、「言葉」ではなく「行為」を通してさりげなく見せる工夫が必要です。
反対に、マンションでの殺人の後始末が、ややずさんに思えます。もう少し筆を割いて、「これならアシがつかない」と読者を納得させる描写が必要でしょう。ゼンちゃんはマイラだから、そこまで神経を使って後始末しなくても逃げおおせるのかもしれませんが、この時点では読者は、マイラとはなんなのかがよくわかっていません。よって、後始末の描写を緻密にするか、マイラの特殊性をもっと具体的に表現するか、どちらかがこのシーンには必要だと思います。そうすることで、小説内のリアリティー(マイラの存在の本当っぽさ)が格段に増すはずです。
物語の作りかたで気になったのが、偶然が多すぎる、という点です。ほとんどすべての登場人物のあいだに、なんらかのつながりが発生する。それによって過去が判明したり謎が深まったりと、スリリングではあるのですが、「こんな偶然ってあるかなあ」とふと思ってしまったりもします。現実では、小説以上に驚きの人間関係が発覚することが多々あるにもかかわらず、なぜか読者は、小説内の「偶然」には厳しい態度を取るものです。小説は虚構の世界だからこそ、リアリティーの構築に神経質にならなければなりません。「偶然」のさじ加減について一考してみてください。
いろいろ言いましたが、『マイラ』は着想、謎解き、物語のダイナミズムなどを兼ね備えた、とてもおもしろい作品です。「どうなるんだろう」と展開が気になって、途中で読みやめることができませんでした。どんどん書いていってください。信頼できる「読み」をする友人などに作品を読んでもらい、客観的な指摘を受けることも有効でしょう。上で私が述べたことも、頭の片隅にでも置いていただければ幸いです。
『若草』は、平安時代と明記されてはいませんが、平安っぽい時代を舞台にしたファンタジーと言えるかと思います。しかしそのわりには、言葉の選びかたが平安っぽくありません。読者を異世界に没頭させるためには、文章からその世界の匂いを発散させる必要があります。たとえば、中納言と中将の見分けが(字面からは)つきにくいので、源氏物語みたいにべつの呼び名(あだ名)をつけるとか。そうすれば、雅な感じも増すし、一石二鳥です。中将の名字が佐久間というのも、平安風の小説世界にややそぐわない気がします。名前はその人物や住んでいる世界を象徴する、とても重要なものなので、雰囲気をかき立てるような命名を心がけてみてください。
同性愛、近親相姦、ジェンダー逆転風味など、私はとても好きでした。最後の一文もきまっています。これらの主題を活かすためにも、雰囲気づくりを万全にしてください。作品の雰囲気を作るということは、作者が作品からもう一歩離れて、俯瞰的視野から作品世界をコントロールする、ということです。それによって、登場人物は万全に構築された作品の雰囲気のなかで、よりいっそう自由に動きはじめることでしょう。今回は残念でしたが、今後もぜひ、書きたい世界をひるまずに書いていってください。
まとめ。
いくつかの作品で、「心の闇」「心の中の闇」といった表現が散見されました。これはいけません。はっきり言って陳腐です。「『心の闇』と表現されるものの実体はなんなのか。はたしてそんなものはあるのか」ということを追求するのが、小説の古くからのテーマのひとつなわけですから、ズバリ「心の闇」などと書いて済ませてしまうようでは、小説のアイデンティティーの崩壊です。簡単にひとをカテゴライズするセンスの持ち主なんだな、と思われるのは、書き手の敗北です。易きに流されず、慎重に言葉を選びましょう。
そういう小さなところから、作品のリアリティーが生まれ、小説世界が盤石なものになるのではないかと、多大な自戒を込めて、私は思っています。
|
●滝本竜彦
『鴨川ホルモー』には作者の小説家としての力量が感じられた。小説家の力量とは何か? 具体的には私にもよく分からない。ただ分かるのは、「いまの私にはとてもこんな小説を書くことはできない」ということだけである。こんな荒唐無稽な設定の話を書く勇気がいまの私には無い。こんな前例の無い話を、最後まで書き上げる粘り強さがいまの私には無い。しかも『鴨川ホルモー』は前例が無いほど荒唐無稽でありながら読んで普通に面白いのである。久々に時間を忘れて小説を読んだ。小説家としての力量が感じられた。勇気、粘り強さ、自分を信じて書き続ける力……そのようなものを『鴨川ホルモー』から強く感じた。この作品は小説であり、この作者は小説家だと思った。文句なしの大賞である。 |
|
●村上達朗
今回は全会一致で万城目学氏『鴨川ホルモー』に決まった。まずはそのことを喜びたい。タイトル、文章、内容、そのすべてにおいて、一頭地を抜いている。人の好みはそれぞれだが、いいものは好みを越える。その見本のような出来映えの作品だった。ただ一点、気になるのは、ほかの選考委員からの指摘にもあるように、作風がやや森見登美彦に似ていることだ。京大生と京都を題材にしているという表面上の類似でなく、物事の面白がり方のセンスが似ているのかもしれない。それと、枚数がやや多い。このふたつが、改稿でどうなるか。大学生たちの不思議なパワーが面白可笑しく炸裂する受賞作が、改稿によってさらにパワーアップしてくれることを、いまから楽しみにしている。
以下、ほかの最終候補作について、ぼくの意見を書いておきたい。
墨野貴子氏『マイラ』も評価は高かった。受賞に一歩至らなかったのは、作品としての完成度に問題があるせいだと思う。文章と内容にはいわく言いがたい熱気があり、そこは魅力なのだが、過剰すぎるきらいがある。悪く言えば、言葉を垂れ流している感じで、とりとめがないのだ。おそらく、作者が作品と距離をとれないのだと思う。だから長くなり、必要以上に描写が細かくなり、作品全体とディテールとのバランスが壊れる。この欠点を直すには、一度書いたものを、推敲時には読者のつもりで読んでいくことだ。今後は、この作業ができるようになるかどうかだと思う。墨野氏にはほかにも応募作があり、それを読んでも同じことが言える。想像力、面白い題材で書く力、意欲は十二分にある方だと思うので、選考委員の講評を参考にして、作品の完成度をいかにあげるかという課題に取り組んでいただきたいと思う。
昭島瑛子氏『僕の半分』も、ぼくは好きだった。派手さはないが文章が正確で、人物との距離感にほとんどブレがない。展開にも面白み、意外性があり、最後はほろりとさせられる。背伸びをせず、悪達者なところがなく、等身大の人物を等身大の筆致で書いている。そこに好感をもったが、問題はそれ以上ではないというところにある。ここが作家デビューのむずかしいところで、小さくまとまっていては、デビューはできないのだ。また、どこからもらってきたのか、「自分探し」などという気恥ずかしいテーマを主人公に語らせてはいけない。作家には、そうしたテーマを恥ずかしいと思うセンスが大事なので、それに気づくようになれば、「等身大の物語」にもきらりと光る魅力が備わるようになるのではないかと思う。
俊多氏『とりかえっこ』にも同様のことが言えると思う。登場人物もストーリー展開もいいかげんで面白く、読後感も悪くない。あえていえば、作者も含め(笑)、すべてがいいかげんで、脱力している世界なのだが、ぼくはそこがなかなか面白いと思った。しかし、それ以上ではないのだ。「脱力世界」を支える強靭な芯がないので、本当の意味で主人公の女の子に感情移入ができないのである。おそらく作者にそこまでの自覚がないことが、この主人公の魅力を十全に引き出せない理由だと思う。あと一歩も二歩も踏み込んで、読者を心底脱力させるような作品に仕上げられる力を養ってほしい。
南野海氏『大和撫子王女様』は応募作の中ではいちばん商業的で、その意味では完成度の高い作品だった。いわゆるライトノベルに属する作品で、作者が楽しんで書いていることはよく伝わってくる。文章に下品なところがあるのはいただけないが、それ以外はキャラもストーリー展開も、意外性も、まとめかたも、どれをとっても形ができている。しかし、それだけなのだ。これは作者の意識の問題だと思う。既成の価値観に自作を合わせるばかりでは、自分がなくなる。自分がなければ、どうやって独自性をアピールできるのか。ライトノベルであれなんであれ、独自に光るものがあって初めて作家デビューできるのだが、それがなんなのか最後まで見えなかった。
沖田リエ氏『若草』は、平安朝(?)に材をとったファンタジーで、文章も悪くなく、評価も高かった。この作者も、作者自身が耽美な世界に酔ってしまっているところが問題で、そのために書き方に客観性がない。酔わせる相手は読者であって、作者ではないのだということをわかってほしい。また、三人称といえども、あまりに頻繁な視点移動は、読者の頭を混乱させ、感情移入をしにくくさせる。ジェンダーの境があいまいな主人公たち、とくにぼくは片方の竜女のキャラが好きだったが、そうした人物と物語の面白さをうまく読者に伝えるためにも、語り口に客観性を与える工夫をしてほしい。力はあるのだから、あとは作品と自分との距離のとり方を学ぶことだと思う。
ほかの選考委員も書いているように、今回の最終候補作はいずれも面白く、読み応えがあった。小説(作品)を書くという孤独な作業の渦中で、作品との距離をとれなどと言われても、簡単にはできないことなのかもしれない。しかし、ここから先、作家としてやっていくためには、どうしても必要なことなのだ。作家である前に、すべての人は読者なのだから、一度読者の立場に立って自作を読み直してみることである。作家と呼ばれる人たちはすべてその作業を経てきているのだということを知っていただきたいと思う。
次なる自信作をお待ちしております。
|
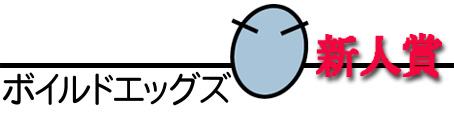
![]()